工学会設備士を取得している方とお会いすると「お、設備設計職の良い人材だ!」と感じます。
建築設備士とは全く違う資格であり、民間資格にも関わらず、何故そのように感じるのかは確かな理由があります。
今回は工学会設備士を取得するメリットを中心に、工学会設備士の試験内容や勉強方法を解説していきます。

工学会設備士は建築設備士と比べられがちですが、建築設備士とは全く別の資格になりますので、その違いは要所要所で私がご説明します。
・工学会設備しの試験内容、勉強方法が分かる。
・設備設計者が工学会設備士を取得するメリットが分かる。
・工学会設備士と建築設備士の違いが分かる。
・工学会設備士、空調設備士、衛生設備士の違いが分かる。
工学会設備士とは
前述しましたが、工学会設備士の正式名称は「空気調和・衛生工学会設備士」と言います。
その他の呼び方として「くうえいがっかい設備士」「SHASEの設備士」「民間資格の設備士」「設備士」などがあります。
学術団体の民間資格
工学会設備士は、空気調和衛生工学会が発行元になります。
空気調和・給排水衛生設備にかかわる技術者の育成とこれに基づく技術の向上を目的としています。
引用元:公益社団法人 空気調和・衛生工学会 設備士資格検定ページ
このように設備設計業務で言う所の「機械設備設計」にあたる民間資格なのですが、
空気調和・衛生工学会という団体は別名SHASEとも言われている、言わずと知れた建築設備、設備設計において基準書はもちろん、様々な工学領域における活動を行っている学術団体です。
「学術団体が認める資格」という響きは、何だかいかにも専門的な資格という感じがしますね。
空調部門と衛生部門がある

工学会設備士の問題と試験日は、空調部門と衛生部門に分かれます。
それぞれ試験日は1日ずつありますので、それぞれの部門に関しての問題がたっぷり用意されています。
設備設計者は機械設備として以下の範囲を取り扱うことになります。
空調換気設備、排煙設備
給排水衛生設備、消火設備、浄化設備など
工学会試験では、それらの専門知識、基礎的知識の両方が求められますので、必然的に機械設備設計に関する全ての専門知識を身につける必要があります。
空気調和・衛生工学会の工学会設備士の試験内容は以下になります。
※引用元:空気調和・衛生工学会HPより
・暖房、冷房、換気空気調和の計画、設計・施工に関する専門知識および環境、エネルギー、安全などに関する専門知識
・ 給水、給湯、消火、排水、衛生器具、し尿浄化槽その他の計画、 設計・施工に関する基本的知識
・ 給水、給湯、消火、排水、衛生器具、し尿浄化槽その他の計画、設計・施工に関する専門 知識および環境、エネルギー、安全などに関する専門知識
・暖房、冷房、換気その他の計画、設計・施工に関する基本的知識
空調部門のみ合格した場合は空調設備士
衛生部門のみ合格した場合は衛生設備士
などインターネットでは散見されますが、
名乗る事は出来るのかもしれませんが、空気調和・衛生工学会が認定を受けれるわけではなさそうです。
建築設備に関する問題数は実は一番多い
機械設備という枠組みの中では、設備設計者が取得できる資格の中で実は問題数が一番多いのは工学会設備士になります。
建築設備士や管工事施工管理技士もありますが、純然たる機械設備設計業務に関する専門知識では、工学会設備士がある意味一番問題数が多いのです。

工学会設備士、建築設備士、1級管工事施工管理技士の純然たる建築設備、設備設計業務に関連する問題数を書きました。
空調部門(試験1日目:計50問)
空調I:20 問
空調II:20 問
空調III:10 問
衛生部門(試験2日目:計50問)
衛生I:20 問
衛生II:20 問
衛生III:10 問
機械設備設計業務に関する問題数合計100問
空調・換気設備:12問程度
給排水衛生設備:12問程度
施工管理分野6問のうち3~4問程度
機械設備設計業務に関する問題数合計約30問弱程度
※建築設備分野として50問あります。
全問題数75問程度のうち施工管理、安全管理などの設計業務に関連例がない問題を15問と差し引いても60問程度と推測
建築設備士の法規や建築関連問題でも設備設計に関係する問題もあり、難しい2次試験もあります。
1級管工事施工管理技士も二次試験がありますので、工学会設備士が一番難しい!というわけではありません。
ですが、単純に正誤問題では建築設備、設備設計業務に関連する問題数は工学会設備士が一番多いのです。
私はこれを知っているから、工学会設備士を取得している方には一目置いています。
きっと、他の設備設計者の方々も同じように思うのではないでしょうか。
工学会設備士と建築設備士の違い

そもそも、工学会設備士と建築設備士は何が違うのでしょうか?
ここをしっかり理解した上で勉強に励むと、試験勉強のモチベーションを維持しやすいです。

工学会設備士と建築設備士は全く違う資格です。
比較すると分かりやすいので作ってみました。
| 資格名 | 発行元 | 法的業務 | 試験の種類 |
|---|---|---|---|
| 建築設備士 | 国土交通大臣 | 建築士にアドバイスができる | 1次、2次試験 |
| 工学会設備士 | 空気調和・衛生工学会 | 特になし | 空調部門、衛生部門 |
大きくはこの3項目です。
建築設備士は国家資格であるのに対し、前述しているように工学会設備士は民間資格です。
ただし、建築設備士ですら特定の内容はありますが、設備設計業務においては基本的に法的に必要な人材ではないのです。
受験の為の実務経験の年数が違う
今度は工学会設備士と建築設備士で微妙に違う実務経験についてです。

工学会設備士と建築設備士の実務経験の違いも
比較を作りました。
| 受験に必要な実務経験 | 指定の理系大学卒業後 | 実務経験のみ |
|---|---|---|
| 建築設備士 | 2年 | 9年 |
| 工学会設備士 | 0年 | 7年 |
重要な所は以下になります。
・建築設備士とは実務経験年数で2年の差がある
・理系の指定大学卒業で実務経験年数0で受験が可能
・全く畑違いの方でも7年あれば受験可能
大学の指定学科卒業後に実務経験無しで受験可能な事は大きいです。
建築士の2級建築士のようなイメージですね。
また建築設備士と2年の差があることにより、工学会設備士を取得してから建築設備士を受験するという流れが出来上がります。
つまりその時のあなたは、工学会設備士と建築設備士両方を取得した素晴らしい人材と判断されます。
建築設備士と工学会設備士どちらが有名?
やはり世間一般的には、国土交通大臣認可の建築設備士の方が資格名としては有名だと言うことです。
資格の難易度などでも出てきますが、建築設備士は特に6時間にも及ぶ2次試験である筆記と作図が難しいのです。
それをクリアする為には、設備設計としての非常に高いレベルの知識が求められます。

建築設備士は国家資格でしかも知名度もあるのなら、工学会設備士を取得するのはあまり意味がないのでは?
そう思う方は是非次の項目も読んでみてください。
工学会設備士を取得しているメリット
前の項目で建築設備士と工学会設備士を比較内容を解説し、結局は建築設備士の方が知名度がある。。。
という所で終わってしまいましたが、知名度や難易度を踏まえても工学会設備士を取得するメリットはあります。
3つ程解説します。
民間資格だからこそ評価される

ご自分が工学会設備士を取得した状態をイメージしながら読んでみましょう。
工学会設備士を取得したあなたを周りはどのように見られるでしょうか?
- あなたの上司はどのように考えられるでしょうか?
- 同僚や部下はあなたの事をどのように見られますか?
- 転職活動中、転職予定であれば、面接先はどのように考えられるでしょうか?

設備設計のお仕事に就いて5年程になりますが、資格は一つもありません。

設備設計は3年程ですが、工学会設備士を取得しています。
建築設備士を受験予定です。
どちらに将来性を見出しやすいですか?

他社で設備設計の仕事をしていましたが、A社に転職を考えています。資格は何も持っていません。

施工管理の仕事をメインに行っていましたが、設備設計のお仕事をしたく転職を希望しています。
資格は1級施工管理技士と工学会設備士を取得しています。
あなたが面接管なら育成枠としてどちらを採用しますか?
工学会設備士は極論、設備設計業務においては必至資格ではありません。
ですが、それを敢えて取得するあなたに対する相対的評価は少なくとも一定のモノがあります。
それが空気調和・衛生工学会の狙いの一つではないかと私は考えています。
設備設計への転職活動を早く開始できる。

現職が設備設計の方はもちろんですが、管工事の施工管理のお仕事をされていて設備設計職への転職を考えている方にとって、ご自分のアピールポイントに悩む方もいらっしゃると思います。
設備設計職に関係する資格では設備設計1級建築士はもちろんですが、建築設備士を取得出来ていれば強力なアピールポイントになります。
ですが、建築設備士は前述したように受験に必要な実務経験が比較的多い事に加えて、1次試験と2次試験に別れています。
1次試験を受験して2次試験合格発表まで約半年の期間があります。
転職は出来るだけ早く、短い期間で行うべきです。
そんな時に工学会設備士の出番です。
工学会設備士なら試験は2日間で終わりますので、建築設備士よりも早い段階で履歴書に設備設計関連の資格を記載できる事になるのです。

転職の際、履歴書に設備設計関連の資格記載の有無は非常に重要です。
工学会設備士は、あなたの将来性を早い段階でアピールできるチャンスなのです。
建築設備士を受験する際に非常に有利
順当に進めれば、工学会設備士を取得した2年後には建築設備士の受験が可能となります。
建築設備士は建築一般知識、法令、建築設備に関する試験なのですが、建築設備に関しては、電機設備の内容も加わりますので出題範囲が非常に広いです。

それなりの勉強期間が必要になりますが、工学会設備士で機械設備に関する勉強をしておけば、電機設備に関する勉強にもその他の勉強に時間を費やせる事になりますので、有利な条件です。
工学会設備士と建築設備士の試験内容では、空調換気設備、給排水衛生設備に関する出題問題はそこまで変わらないのですから。
建築設備士の取得のメリットや勉強方法は以下の記事にまとめています↓↓
空気調和・衛生工学会設備士の勉強方法

それでは、工学会設備士取得の為の具体的な勉強法方法を解説します。
他の資格試験の記事でも書いているように資格の勉強方法の基本は反復です。
勉強方法についての重要事項を以下にまとめました。
基本的な事を守って勉強すればそこまで難しい試験ではないという事を念頭に読んでみてください。
・参考書と過去問両方を用意し、参考書→過去問の順番で行う
・勉強しない日を1日は設ける。※その日を総復習の日としても可
・参考書と過去問のページ数を試験日までの日数で割る
・毎日勉強するページ数を理解して、予定を立てる
・過去問は必ず3回以上は繰り返す
・3回繰り返しても間違える箇所を一つのノートにまとめる。
以上が私のオススメする勉強方法の基本です。
①参考書で勉強する
それでは工学会設備士の勉強の為のオススメ参考書は以下になります。
出版はオーム社ですが、編集に空気調和・衛生工学会が関与しています。
民間資格は、その資格発行元の参考書で勉強するのが基本です。
②過去問をひたすらこなす
工学会設備士の過去問は市販では販売されていません。
こればかりは空気調和・衛生工学会のHPで購入するしかなさそうです。
以下にURLを貼っておきます。
まとめ
それではまとめに入ります。
・工学会設備士は学術団体の民間資格であり建築設備士とは別物
建築設備士との違いのまとめ
| 資格名 | 発行元 | 法的義務 | 試験内容 | 機械設備設計に 関係する問題数 | 実務経験 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学会設備士 | 空気調和・衛生工学会 | 無し | 空調、衛生部門(連続2日) | 100問 | 指定学科の大学なら0年、実務のみは7年 |
| 建築設備士 | 国土交通大臣 | 無し:建築士へアドバイス | 1・2次試験 別日 | 約30問弱程度 | 指定学科の大学なら2年、実務のみは9年 |
・工学会設備士取得のメリット
民間資格だからこそ取得することで、ご自身の設備設計者としての相対的評価に繋がります。
転職活動に有利になり、かつ試験勉強、合格までの期間が短いので転職の際の履歴書に早く取得資格が記載できます。
また、工学会設備士合格の2年後の、建築設備士の受験の為の勉強にも非常に役立ちます。
・工学会設備士の勉強方法
・参考書と過去問両方を用意し、参考書→過去問の順番で行う
・勉強しない日を1日は設ける。※その日を総復習の日としても可
・参考書と過去問のページ数を試験日までの日数で割る
・毎日勉強するページ数を理解して、予定を立てる
・過去問は必ず3回以上は繰り返す
・3回繰り返しても間違える箇所を一つのノートにまとめる。
以上です。
工学会設備士が非常にメリットのある資格だという事がお分かり頂けたでしょうか?
願わくば、工学会設備士を取得して私の会社に来てほしい程です。
設備設計者として良い人生になるように願っております。
pinky

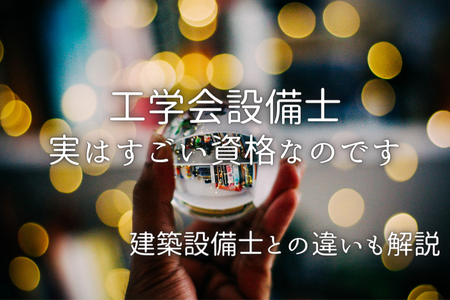
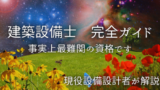




コメント